国語の授業で教わることと、国語の入学試験で問われることの違い
一般的に、高校入試や大学入試の国語や現代文の試験は、受験者の「文学的センス」のようなものを問うているのではないとされている。客観的(つまり、採点基準が明確で、誰が採点しても同じ点数になるよう)な試験を作るのであれば、解釈が多様になるような問題ではなくて、解釈が一通りにしか決まらないような問題しか出せないということである。つまり、誰が読んでも同じようにしか解釈され得ないような部分しか出題されないということである*1*2
しかし、「いや、そんなことはない。自分が受けてきた試験では『作者の気持ち』のような解釈の分かれそうな問題が出ていた」と主張する方、あるいは、「実際に作者が自分の出題文の問題を解いて間違えたりするではないか」と主張する方、実際に高校入試やセンター試験などの問題を見ていただければと思う。
たとえ「作者の気持ち」を聞かれていたとしても、それは出題文のみの情報から論理的に考えてその解答しかありえないような出題のされ方しかされていなはずある。「作者の気持ち」であろうが何であろうが、とにかく国語の入学試験で問われるのは、回答者が持っている知識でもなければ、文学的センスでもない(ただし漢字の意味や言葉の定義などといった知識、そして人間についてのちょっとした知識*3は必要である)。
作者でも解答を間違えるのは、出題文の部分以外の情報や、自分の持っている知識、あるいは「解いている自分の気持ち」を答えてしまったからである*4。
もっといえば、「作者の気持ち」を問う問題は、本当に作者が思っていた気持ちを答えるのではない。その文章から論理的に読み取れる限りでの書き手の気持ちを問うているのであって、実際に本当の作者がどう考えているかは解答とは無関係である。むしろ、作者が何か表現したい気持ちを持っていたとして、それが誰が読んでも同じように読み取れるように書けているということもアヤシイのであって、回答者はあくまで、出題された文章のみから読み取りうる想像上の作者を想定し、その「気持ち」を読み取ることが求められているということである。
極端な例を考えてみれば、その文章を書いたときの作者の気持ちが「今日の晩御飯は何にしようか」であったとしたならば、それが本当の「作者の気持ち」である。しかし、文章中にそんなことは書かれていないのだから、答えとしてはありえない。文章中から得られる以外の情報に関しては何も尋ねられていないのである。
国語の問題を作成する人は、いかに他の答えがありえないような問題を出すか、というところに心を砕いているらしい。もし、例えば選択式の問題で、複数の選択肢が同等に正解であると認められるような問題を出してしまった場合、それは「悪問」扱いされることになる。
意外だっただろうか。自分はこれを初めて知ったときにその意外性のあまり衝撃を受けた。なぜ意外だったのだろうか。
それは端的に言って、国語の授業で教わることと国語の入学試験で問われることが違うからではないだろうか。国語の授業では、実際に「文学的センス」や「鑑賞する力」、「文章を味わう力」のようなものが教えられ、問われている。学習指導要領にそれを教えなさいと書いてある*5。
もちろん、文章中に「そのとき雨が降っていた」と書かれていたときに、「そのときの天候は何ですか」と問われ、「そのときは晴れていた」と答えるのは明らかに間違いあり、「そのときは雨が降っていた」が唯一の正しい答えである。しかし教室内では、論理的に考えて解釈が多様にあり得るような場合であるならば、答えを1つに絞らないように、多様な解釈を認めることが理想とされている*6。たとえば「そのときは雨が降っていたということだが、そこにいた主人公の気持ちはどうであったか」と問えば、解釈は多様にあり得る。要するに、解釈が一通りに定まるか多様となるかは問い方次第である(もっとも教室内ではこの2タイプの問いが区別されないまま問いかけが行われているような気はするが)。
しかし国語の入学試験では、冒頭で述べたように、答えが1つにしか決まらないような問題しか出題されないのである。当然、子どもは混乱するだろう。
主要5教科のうち、国語以外の数学、英語、理科、社会では、授業で教わることが定期試験でもそのまま問われるし、それが入学試験でも問われる。しかし国語の場合は違うのである。
この事実は中学校くらいで教わりたかったのだが、自分は浪人中に予備校で教わった*7。こういったたぐいの国語に関する誤解は他にも多くあるんじゃないかと思う。
例えば、「小説には必ず起承転結があり、小説に出てくる記述は必ず後に何らかの結果と関係する」といった誤解である。村上春樹の『海辺のカフカ』ではイワシとアジが空から降ってくる。ふつうのお話だったら、イワシとアジが空から降ってきたら、上空で何かが起きているとか、登場人物に超能力があるだとか、そういう話になるだろう。しかしこの小説では、これが直接の原因となって後の話の展開を変えたり、大きな伏線となっていたかというと、そうではない(だったと思う)。
読みは基本的には自由であるはずで、ある記述に過度に意味を読み取るのも、何の意味もない記述として通り過ぎるのも、どちらも認められてしかるべきなのだと思う。実際の世界もそうで、通り過ぎた家の2階の窓から何かの拍子にイワシあるいはアジが落ちてきたとして、あとで笑い話のネタにはなるかもしれないが、後に自分の身に引き起こされる何かの「伏線」になっていると考える人はまずいないだろう*8。世界のある部分を切り取ったときに、それが起承転結になっていることなんてそうそうないのであって、全ての小説に起承転結の構造があると期待するのは、お門違いなんじゃないのか。
もう一つ誤解の例を挙げたい。国語の試験では、「登場人物の行動の理由や気持ち」問われることがあるのだが、この問いを可能とするには、「登場人物の行動の理由や気持ちは言語化可能である」という前提を一段上に置かなければならない。
これも一つの誤解ではないだろうか。我々の行動の理由や気持ちがそんなにしっかりと、他人に説明できるように言語化できるなんて、いったいだれが決めたのだろうか?*9
世の中にあふれる小説は、主題が何なのかがはっきりとしていて、誰でも同じような感想を得られるような、教科書に載っている小説のようなものばかりではない。
しかし近代国家の法体系は、行動の理由が言語化にできるという前提に立っているし、これは近代特有の誤解なのかもしれないなあ、と考えたりする。いや、古代ギリシャからそうだったのかもしれない。まあ、わかりません。
さて、ところが実は、1999年まで東京大学入試の国語の第二問では、文章や詩を読ませて、回答者が感じたことや意見を書かせる、という問題が出題されていたのである。これをどう考えるかについてはいまのところ答えを持ち合わせていないので、今後の課題としたい。この問題については以下の本に詳しい。学術書ではないが、「東大入試国語の第二問」の雰囲気がわかると思う。
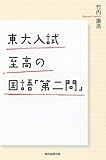
- 作者: 竹内康浩
- 出版社/メーカー: 朝日新聞出版
- 発売日: 2008/08/08
- メディア: 単行本
- 購入: 9人 クリック: 64回
- この商品を含むブログ (17件) を見る
ちなみにこれはこれでまた面白いことなのだが、現在の東大入試の国語の現代文では、文章に傍線が引いてあって、その箇所について「〜とあるが、それはなぜか説明せよ」、あるいは「〜とはどういうことか説明せよ」という2パターンの問題しか出題されない。前者は理由を尋ねていて、後者は具体的な言い換えを求めている。そして、どちらも文章中に必ず答えがあり(つまりその文章のテーマに関する既有知識は不要だということである)、論理的に考えれば解釈が一通りにしかありえないような問題になっているのである。
最後に一点、触れておきたい。この記事の中で「論理的」という言葉をたくさん使ったが、これもマジックワードであって、本当は厳密な定義を与えないと議論が曖昧になってしまう。「誰が読んでも同じ解釈になる」というのもそうで、どうやってそれを判断することができるのか、という問題もある。しかしそこまで論じる力量はなかったので、そのあたりはご寛恕いただければ幸いである。
参考文献
- 新潮社, 2013, 「受験とポストモダン――自分の文章が使われた入試問題を問いてみました」『新潮45 5月号』, pp. 236-257.
- 鈴木義里, 2011, 『大学入試の「国語」――あの問題はなんだったのか』三元社.
*1:少なくともここ30年くらいの入学試験においてはそうである。1970年代やそれ以前には、論理的に読んでも解答が多様に考えられてしまうような問題も存在していたようである(鈴木 2011)
*2:特に選択式の問題であればこのように言えるが、記述式の問題(例えば「〜とはどういうことか説明せよ」)という問題出れば、正答となる記述は一つには定まらない。例えば出題者が想定した正答とくらべて助詞の使い方や句読点の位置が違っているくらいであれば、同じ要素が書かれているのであるから正答とすべきである。したがってこの場合、一字一句全く同じ文章が「正しい解釈」として存在しているのではなく、ある解釈の範囲に含まれている解釈を「正しい解釈」として正解とするものだといえる。その範囲に含まれないもの、例えば問題文中に「そのとき雨が降っていた」と書いてあったとき、「そのときの天候は何であったか」と問われて、その部分を「晴れている」と解釈するようなことがあれば、それは明らかに「正しくない解釈」であるといえる。しかし「雨が降っていた」あるいは「天候は雨だった」という回答は両方とも正答とすべきである。以上、この記事では、「誰が読んでも同じ解釈になる」という状態について、「正しい解釈」には幅があるという想定をしている。またこのような前提において、「説明的文章」であろうが「文学的文章」であろうが、「誰が読んでも同じ解釈になる」読み方を問うような問題を作成することは可能である。
*3:というのは例えば、「誰かがため息をついた、という描写は、その人の緊張がほぐれたことを意味する」だとか、「誰かが泣いている、という描写は、その人が怒っていたり悲しんでいたりといった平時の感情ではない感情を持っているときである」だとか、「誰かが頬を赤らめた、という描写は、その人が恥ずかしがっているときである」だとかのことであり、一般的に言えば、「描写がどのような感情・思考を示しているのかを対応付ける知識のセット」のことである。端的に「常識的な人間感覚」と言っても良いかもしれない。実はこの知識をいかに常識的なものに近づけるか(例えば「ため息」は「緊張のほぐれ」であり「怒り」の描写ではない、というように)が入試の小説問題で問われている力のひとつだと思うのだが、それにはまた別稿を期したい。
*4:この点について、新潮社の月刊誌『新潮45』 2013年5月号の特集「自分の文章が使われた入試問題を解いてみました」が非常におもしろい。作者が実際に解答を間違えている。それについてある作者は、「文章全体で言いたかったことは違うのだけれど、たしかにこの部分だけ抜き取ったらそのように読める」、というような感想を述べていたりする。
*5:ここで注意しなくてはならないのは、学習指導要領には、そういったセンスだけではなくて、文章を論理的に読んだり書いたりするための言語技術的なことを教えなさい、とも書いてあるということである。センスだけを培いなさいと言っているわけではない(実際の教育現場ではそちらに偏りがちのように思えるが)。しかし個人的には、文章をある意味で論理的でないように、感情的に読むような力(うまく表現できませんが)も人間には必要なのだと思うし、学校で教えてしかるべきだとは思う。
*6:国語科教育を論じる文献を読んでみれば、唯一の解釈に子どもを閉じ込めるようなことは忌避されていて、教員の業界ではちゃんと、建前上ではあるがそういう認識はあるのである。しかし実際そうでないのは、多様な解釈を認めるような授業を行うのがかなり難しいから、あるいはそういう授業を行うための教師教育が十分に行われていないからではないかと自分は考えている。もっとも、このような状況があるからこそ、わざわざ種々の文献で「解釈を固定するな」と主張されるのだろうが。
*7:もっとも、授業で問うことの半分(文章の論理的読解)は試験で問われるけど、もう半分(文章の鑑賞)は試験では問われない、と中学生に伝えてしまったら、国語の授業の半分だけをマジメに受ければよいのだ、という生徒ばかりになってしまうかもしれない。
*8:目の前を黒猫が走り去ったとか、国士無双をツモったとか、そういったことがあったときに、何か運命めいたものや予言めいたものを感じることはあるかもしれないが。
*9:カミュの『異邦人』を読んでみればよい。果たしてそこで「異邦人」の気持ちを簡単に言語化できるものだろうか。もしそれができたのならばカミュは『異邦人』を書く必要がなかったはずである。なぜムルソーはアラブ人を殺したのかと問われ、「太陽が眩しかったから」と回答したとして、それは正解だろうか?